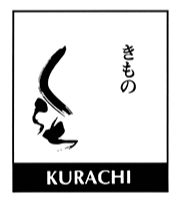きものくらちの小牧店ブログ
切子柄
2020.05.28

陽の光に当たっていると、本当にじりじりと焼けるような暑さになってきましたね。
今日みたいな日は、涼し気なグラスで炭酸水を飲みたくなります。
ガラスは、なんと弥生時代には日本に存在していたようで、遺跡から勾玉(まがたま)などの装飾品が発見されています。
ただ、この時代のものは、おそらく日本で作られたのではなく、海外からもたらされたものだと考えられています。その後、2000年ほど前には日本でも作られるようになりましたが、徐々に衰退し、再びガラスが広く作られるようになったのは、18世紀の初め。
鏡、メガネ、かんざし、風鈴などが主でしたが、次第に食器類が作られるようになりました。
昔は「瑠璃(るり)」や「玻璃(はり)」と呼ばれていましたが、江戸時代から「ぎやまん」、「びいどろ」と呼ばれるようになり、その後「ガラス」という呼び方が一般的になりました。
江戸いろはかるたの中に、「瑠璃も玻璃も照らせば光る」ということわざがあります。「本当に優れたものは、他の多くに混じっていても美しく輝く」という意味だそうです。
と言う事で、今日は、”多くの人の中に紛れても、美しく輝く浴衣姿になれる浴衣”をご紹介。
江戸切子柄の水浅葱色、白銀色の美しい浴衣。涼し気に着こなして頂きたい浴衣なので、帯留めにも同系色を使用した、ガラス製のものをあわせてました。
浴衣 撫松庵 セオアルファー 水浅葱/白銀/白
半巾帯 えんさが ポリエステル ふくれ織 薄墨色/麻の葉 & 白/薄墨色のライン入り
帯締め 白/けしむらさき
帯留 ガラス製 白/水浅葱/白銀